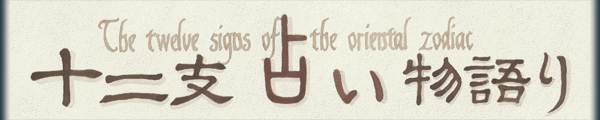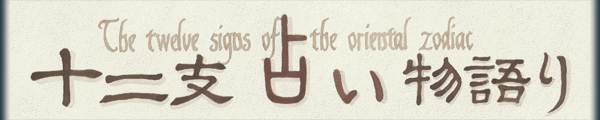|
干支(十干と十二支)は、殷王朝の時代(紀元前1500年〜紀元前1100年頃)には日を表すために用いられていました。陰陽五行説が成立し、前漢の初期(紀元前120年頃)に最初の暦・太初暦が編纂される頃には、干支は、年、月、日、時間と方位、季節などを表すために用いられ、陰陽や五行も配当されるようになりました。

一般的に十二支といえば、鼠・牛・虎…という十二支獣を思い浮かべますが、本来の十二支は、天干に対する地支です。大地を支配し、地上に生きるもの全てと方位と時の流れを司るとされ、一年十二ヶ月の季節の循環と命のサイクルをあらわすシンボルなのです。 十二支に対して十二支獣のイメージが定着したのは、後漢の時代・紀元100年頃に王充が、本来の意味の十二支の概念に、それぞれの性質に近いイメージの身近な動物をあてはめて普及を図ったためとされています。

本来の十二支には、年、月、日、時間、方位や季節、そして五行や陰陽や易の卦が配当されて、それぞれの支の性質、性状やイメージを構成しています。例えば、十二支の一つ『午』は、陰陽の分別では陽性に属し、五行(木火土金水)では火性に属し、方位は南、一年の中の月では6月で季節は夏、一日の中の時間では真昼の午前11から午後1時の間、に配当されています。反対に『子』には、陰陽は陽、五行は水、方位は北、季節は冬、時間は真夜中の午後11時から午前1時が配当されています。

十二支が日本に伝わったのは、六世紀半ばとされていますが、そのときにはすでにお馴染みの十二支獣のスタイルが成立していました。暦法の論理として本来の意味の干支とともに宮中や寺院の奥深く秘伝・秘術として伝えられていきましたが、江戸時代には広く一般に流布し、十二支=十二支獣として普及するうちに、十二支に配当された動物のイメージの方が強くなっていきました。十二支獣のイメージに迷信、盲信も加わって十二支占いもまた私たちの生活に深く根を下ろしていったのです。

私たちの生活の中にも干支や十二支に関係する言葉はたくさんあります。地球の北極と南極を結ぶ経線『子午線』や、『午前』『正午』『午後』、『東南辰己の角部屋』や『戌亥の蔵』、大正13年甲子の年に完成した『甲子園球場』の命名の由来も、みな十二支が年や月や時間、方位を表すことに由来します。十干と十二支の組み合わせは60通りです(60干支)が、生まれた年から数えて61年目に、その人が生れた年と同じ干支の組み合わせが巡ってきます。これを『還暦』と称し、赤子に戻って出直しの意味で赤い頭巾に赤いちゃんちゃんこを着てお祝いをする習慣も干支に由来するものです。

祖先の時代から現在に至るまで、十二支は私達にこよなく愛し続けられてきました。十二支は、先人の知恵の詰まった、最も身近な生活の「ものさし」なのです。
|